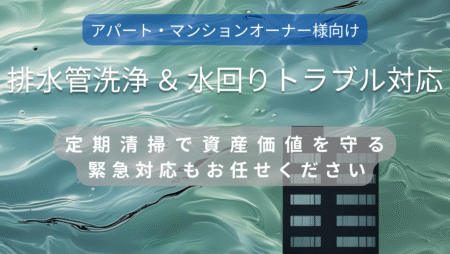すべての工事に事前調査は必要
サブタイトルにすべての工事に事前調査が必要と書きましたが、実はややこしいことに一部例外も存在します。
ただし、一般的な認識としては「ほぼすべての工事に事前調査が必要」と考えて差し支えありません。
なお、建物が古いか新しいか(たとえば2025年に建ったかどうか)に関係なく、事前調査は必ず必要です。
何をいまさら、と思われている方もいるかもしれませんが、あまり状況を把握できていない方が多いと感じたので事前調査についての情報を共有させて頂きます。
解体等工事には該当しないことから、事前調査を行う必要がないとされる作業
以下の作業については、建築物等の解体等には該当しないことから、事前調査を行う必要がない
(ア)除去等を行う材料が、木材、金属、石、ガラス等のみで構成されているもの、畳、電球等の石綿が含まれていないことが明らかなものであって、手作業や電動ドライバー等の電動工具により容易に取り外すことが可能またはボルト、ナット等の固定具を取り外すことで除去または取り外しが可能である等、当該材料の除去等を行う時に周囲の材料を損傷させるおそれのない作業。
(イ)釘を打って固定する、または刺さっている釘を抜く等、材料に、石綿が飛散する可能性がほとんどないと考えられる極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業。なお、電動工具を用いて、石綿等が使用されている可能性がある壁面等に穴を開ける作業は、これに該当せず、事前調査を行う必要があること。
(ウ)既存の塗装の上に新たに塗装を塗る作業等、現存する材料等の除去は行わず、新たな材料を追加するのみの作業
(エ)以下略
「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策マニュアルのP.89~P.90から一部を引用」
(ア)について
つまり、石綿を含まない材料を、周囲を壊さずに簡単に取り外せる作業は事前調査の例外となります。
気を付けないといけないのは、例えば木材のみで構成されているもの。と言ってもあまり一般的ではないですよね。
ガラスのみ、石のみもい同じです。
そのあたりの文言に注意してください。
(イ)について
この文言を読んで「釘ならいいのか」と思いましたが、釘も短い釘から長い釘まで様々ですし、手打ちじゃなく、機械で打ち込む釘もあります。
極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業と記載されているので、90mmや65mmその他の機械釘を打ち込む作業はアウトだと考えて良いと思います。
打ち込む衝撃で微量でも粉塵が出ます。
次にインパクトドライバーその他電動工具で打ち込むビス(コーススレッド)ビス抜きもです。
これはアウトです。札幌の労基署の安全衛生課に確認致しました。
壁面に穴を開ける作業もアウトです。
ドリルやコアが小さかろうが大きかろうが穴を電動工具で開けるという行為自体アウトだと聞かされました。
つまり、昨今よく行われているエアコンの冷媒管などを通すための穴あけ作業も事前調査が必要なのです。
(ウ)について
塗装をそのまま上から塗りつぶすということはあまりしませんよね。
現状の塗装部分が悪い所は除去等をするはずです。プロの塗装屋さんなどでは塗り替えなどでは下地処理を必ずするはずですので、ほとんどの場合事前調査が必要になると考えられます。
(ア)(イ)(ウ)を読んでどう思いましたか?
私は「じゃあ、ほとんどの工事に事前調査が必要じゃないか!」と感じました。
そうです、その通り「工事の前に事前調査は必要」
そして、事前調査は元請け工事業者の義務なのです。
事実上、ほぼすべての工事に工事前の石綿の事前調査が必要ということになります。
場合によっては、事前調査の結果を所轄の労働基準監督署長と都道府県知事等に報告をする必要があります。
石綿が出ても出なくてもです。
事前調査の報告が必要なケース
・建築物の解体→解体部分の床面積の合計が80㎡以上
・建築物の改修(リフォーム)→請負金額が税込み100万円以上
・工作物の解体・改修→請負金額が税込み100万円以上
以上のケースは石綿が出ても出なくても上記の場所へ報告が必要になります。
では、工事業者(元請け)は今後どうすればよいか
繰り返しにはなりますが、作業前に事前調査を行って結果が出てからの作業開始になります。
じゃあ、事前調査はどうやってやれば良いのだ。
実は石綿の事前調査者という資格があります。
今メジャーなのは
「一般石綿含有建材調査者」
「工作物石綿事前調査者」
この2つの資格を持っている人に調査を依頼すればほぼ間違いありません。
もしくは検索すれば出てくると思いますが、各地域で調査会社があるはずです。
それでもわからなければ地元の解体屋さんに紹介してもらいましょう。
ちなみに札幌市にある我が北嶺建設では弊社取締役と社員1名、計2名が両方の資格を保有しており、事前調査業務を行えます。
ご用命があれば全国どこへでも行く気持ちはあります。
気軽にホームページのお問合せフォームよりお問合せください。
発注者(お客様)の責務
「業者に任せておけば大丈夫」と思いがちですが、法律上は発注者も義務を負っており、完全に無関係ではありません。
実際には施工業者が直接罰せられるケースが多いですが、発注者も「知らなかった」では済まない立場だと言えます。
しかし、お客様のお財布事情からすればこの上ない迷惑な話である。
今までは工事分だけの料金だったものに、事前調査のための費用が上乗せされるからである。
具体的にいくら増えるかは、その調査内容によって変わるので決まりはないが一般的に考えて最低でも3万円前後以上の費用が上乗せされるでしょう。
場合によっては数十万なんてことも考えられます。
それにプラス、アスベストを含んだ産業廃棄物の処理代が追加でかかります。
普通の産業廃棄物とは単価が変わります。
話を少し戻し、責務の話になりますが
発注者(お客様)は、元請け業者に対し、作業基準の順守を妨げる恐れのある条件をつけないように配慮すること(安衛法 石綿則9、大防法 法の18の16)
発注者(お客様)は元請け業者に対し、事前調査に要する費用を適正に負担すること、その他当該調査に関し必要な措置を講ずることにより、事前調査に協力すること。(大防法18の15)
結局のところ、石綿の事前調査や処理にかかる費用は決して安くはありません。
しかし、それを怠れば工事中に石綿が飛散し、健康被害や行政処分、さらには工事中止や追加の費用負担など、もっと大きなリスクを背負うことになります。
つまり事前調査は、「余計な出費」ではなく「安全と安心を確保するための必要経費」です。
そして何より、石綿に関する規制は法律で定められており、発注者も業者もそのルールを守らなければなりません。
最終的には、調査を正しく行い、その結果を踏まえて工事を進めることが、法律を守りながら安心して工事を終えるための最も確実な方法だと言えるでしょう。
元請け業者の方は心配であれば所轄の労働基準監督署へ問い合わせして聞くのが間違いありません。
本日のアスベストに関する記事はここまでとします。
反響等ありましたら、アスベストに関する続編を記事にしていこうと思います。
北嶺建設の平社員より